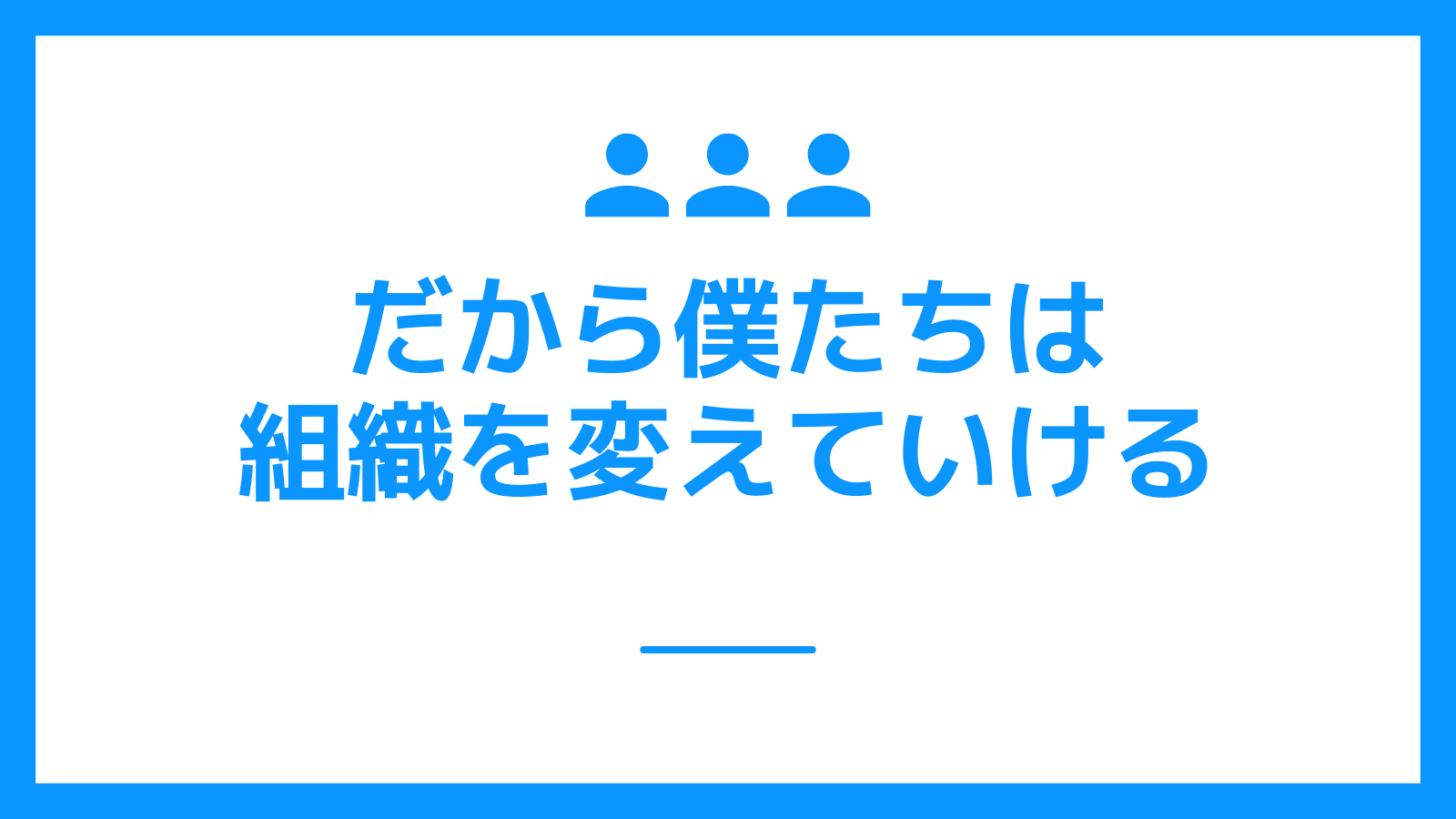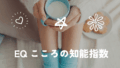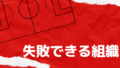本書は、「組織を変えるのはトップだけではなく、一人ひとりが起点になりうる」という強いメッセージを投げかけくれます。著者自身も「現場の社員・メンバーであっても、『自分だからこそ変えられる』という視点で動き出せる」と述べています。
時代が大きく変化する中で、従来型の「統制・命令・管理」という組織モデルでは変化に対応できなくなってきている中で、「ああ、自分には何もできない」とあきらめるのではなく、「自分だから変えられる」「小さく始めて、影響の輪を広げていける」と信じることが、変革の出発点。
「自分のチームの関係性をちょっと変えてみよう」「自分の仕事の意味・価値を問い直してみよう」「自分から主体的に動いてみよう」という小さな一歩が、やがて組織の変化につながる――本書はそんな希望を与えてくれます。
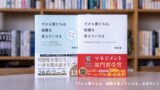
工業社会から知識社会へ
われわれの社会はこれまで「農業社会→工業社会」と変化し、さらに「情報革命」を経て「知識社会」へと移行しています
工業社会では機械やロボットが人の手足を代替していましたが、知識社会ではコンピュータが人の記憶や計算能力を代替しており、人間に残された価値は「暗黙知」「感性」「意志」。このような見えないものを深く理解しないと人の心は動かず、組織は機能しない
そんな今こと、マネジメントは人間性に回帰していく必要があります
僕たちが目指したい組織
知識社会・クリエイティブ社会にふさわしい組織の3つの理想像
●学習する組織:変化を捉え、環境から学び続ける。
●共感する組織:顧客・社会・メンバーに対して「共感」「信頼」「価値共創」を重視する。
●自走する組織:指示・管理ではなく、メンバーが自ら考え、行動し、チームとして成果を出す。
一人ひとりが自分の意思で考え、行動し、仲間と協力して成果をつくる。そんな「自走する組織」に変わるためには、まず“マインドチェンジ”が必要です。
これまでのように「上が決める」「下が従う」という発想から、「みんなで考える」「自分ごととして動く」という意識への転換。
そして、リーダーにも変化が求められます。リーダーはすべてを指示する存在ではなく、メンバーの可能性を引き出し、安心して挑戦できる場をつくる“ファシリテーター”へ。
組織を変える第一歩は、構造を変えることよりも、関わり方を変えること。
「どうすればこの人が輝けるか」「どうすればこのチームが成長できるか」――そんな視点を持つリーダーシップこそが、僕たちの未来をつくっていくのだと思います。
心理的安全性
心理的安全性という言葉がよく使われるようになりました。
でも実際には、「みんなで仲良くしましょう」ではなく、共感と価値をどうデザインするかが本質です。
まず大切なのは、共感をデザインすること。
相手の立場や背景を理解しようとする姿勢、そして「あなたの考えには理由がある」と受け止めること。
たとえ意見が合わなくても、「なぜそう思ったのか?」を丁寧に聞く。
この“共感の設計”があるチームでは、自然と安心して発言できる空気が生まれます。
もう一つの鍵は、価値をデザインすること。
人は「自分の仕事が誰かの役に立っている」「このチームの一員として意味がある」と感じるとき、恐れよりも前向きなエネルギーで動けます。
単に目標を共有するだけでなく、「この仕事でどんな価値を生み出したいのか」を語り合う時間を持つことが、心理的安全の土台になります。
つまり、心理的安全は“優しさ”ではなく、“設計”です。
共感のデザインで心をつなぎ、価値のデザインで目的をつなぐ。
この2つが噛み合ったとき、チームはただ安心なだけでなく、挑戦し続けられる強い組織になります。